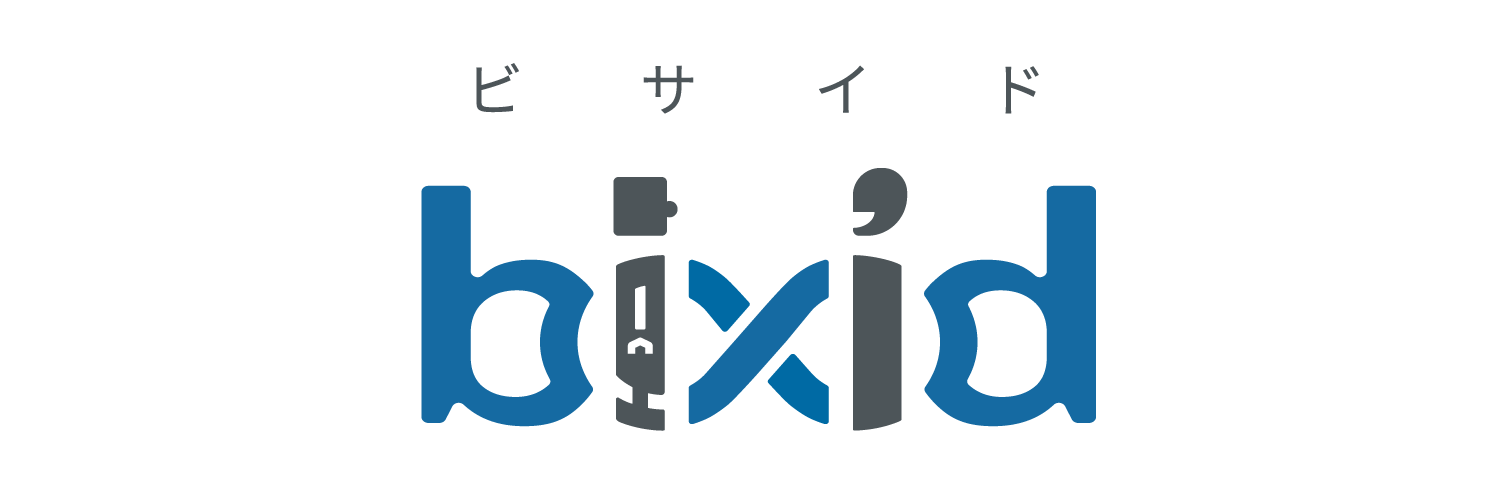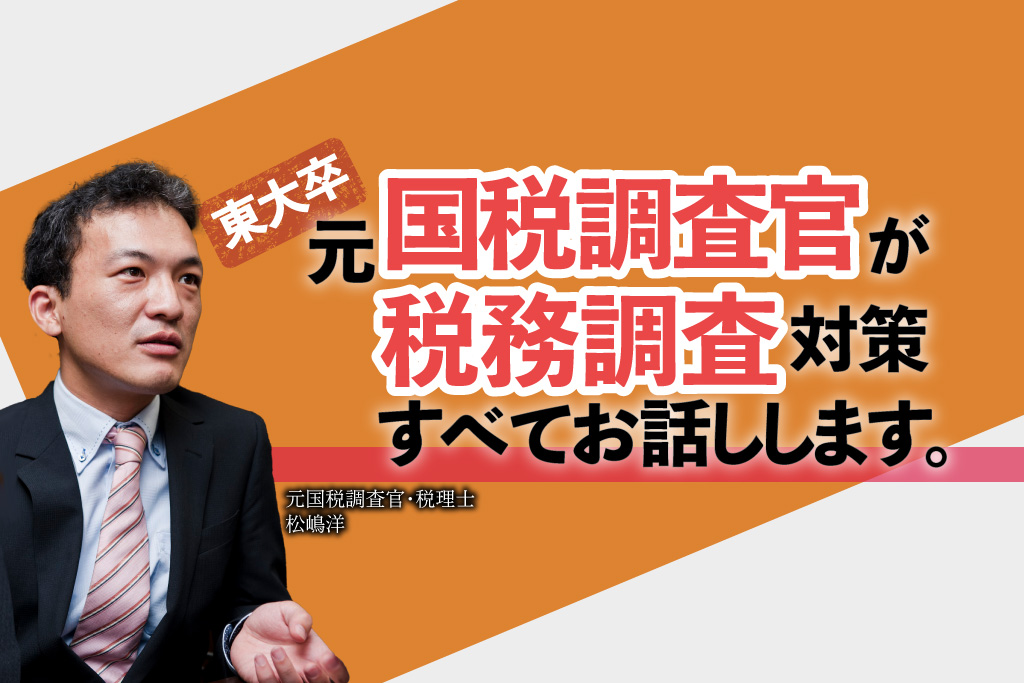
税務調査で最も重要な用語の一つに「承諾」が挙げられます。
税務調査は犯罪捜査ではなく、納税者の同意を前提にした任意調査です。
しかし、任意である以上納税者から「承諾」を貰えば、調査官は基本的にどのような調査をしても問題ないことになります。
この点、国税組織も十分に理解しています。
具体的には、逐一納税者から承諾を取りながら税務調査を行うこととし、若しくは(無言の圧力をかけて)納税者に承諾をさせた上で税務調査を進めています。
しかし、この承諾は単に納税者だけではなく、税理士やその税理士の事務所の職員の承諾もこれに含まれるとした事例があります。
この事例では、税務署に帳簿書類等を預ける「留置き」の承諾が問題になりました。
留置きは必ず承諾が必要な手続きです。
裁判所は納税者から委任を受けた税理士が雇用している、その税理士の事務所の職員から留置きの承諾を貰っていたため、税務当局が留置きをしても違法性はないと判断されています。
税務署は承諾を受ければ、自由に税務調査を進めることができるため要注意であることは税務調査のセミナーで必ず指摘することの一つです。
しかし、実際の税務調査実務では、税務調査を受ける納税者より、税理士の承諾が問題になることが圧倒的に多いです。
税務調査は税理士に委任できますので、納税者が立ち会わないことが多いです。
加えて、税理士は税務署とトラブルになりたくないため、調査官の要望を承諾することが多いからです。
後者について補足しますと、税理士は税務署から資格を貰っていますが、税理士の懲戒事由の一つに「調査非協力」があります。
程度の問題はありますが、税務署の意向を承諾しないと、調査非協力による懲戒処分を受け免許を失うという恐怖が税理士にはあります。
現に、かく言う私も、この前の税務調査で資料調査課の調査官から、脅しを受けました。
具体的には、予定が合わないため調査を先延ばしにしたり、資料の提出を先延ばしにしたりしたいと要望しました時の話。
調査官は、「それは税理士の品位としては問題があるのでは?」という言葉を投げかけました。
私は別にして、税務署の内情を知らない税理士がこのようなことを言われると、「懲戒処分を受けて資格を失うことになる!」と非常に怖い思いをします。
それに止まらず、後輩である税務署にいい顔をしたいと考える国税OB税理士の中には、税者に「調査が早く終わるからもっと協力(承諾)しよう」といった的外れな指導をする方もいます。
いずれにしても、税理士の承諾も税務調査の承諾とされますので、税理士は今まで以上に注意して税務調査に臨まなければなりません。
税理士は納税者を守るために、税務調査の根拠法である質問検査権を徹底的に研究した上で、毅然とした態度で税務調査と闘い、不必要な承諾をしないように注意する必要があります。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。