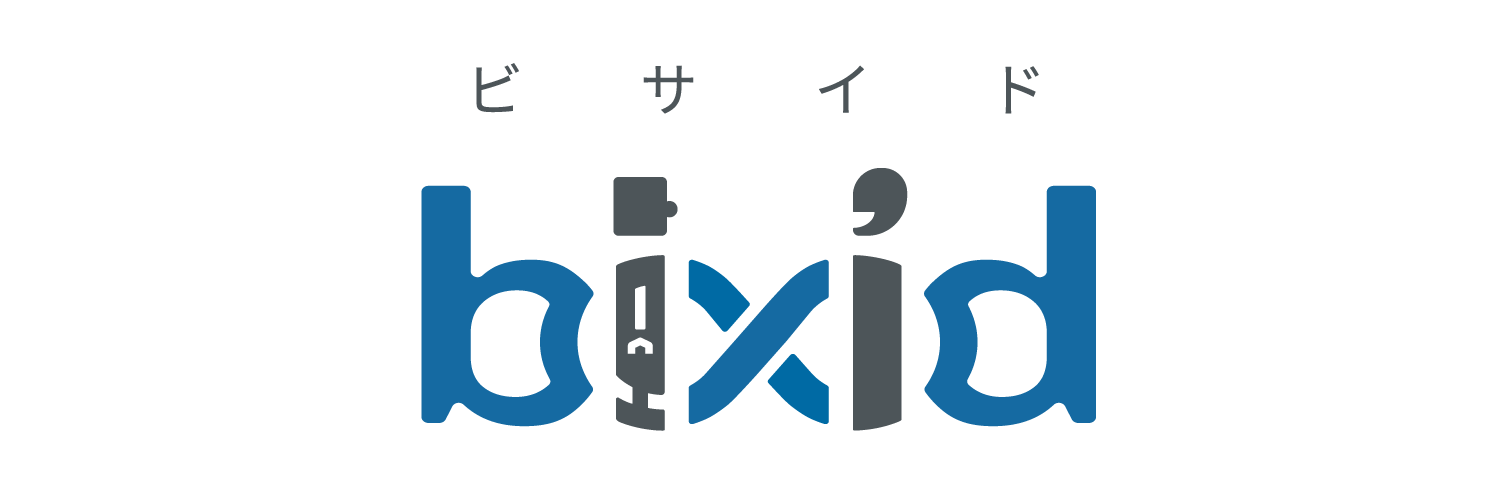所得税法上、個人は原則として日本に住所があるか否かで居住者と非居住者に区分されます。
居住者と判断されれば全世界の所得に対して累進課税で課税されるため、非居住者に比して税負担が飛躍的に大きくなります。
このため、住所の判断が非常に重要になりますが、税務当局が重視するのは1年間の滞在日数であり、いわゆる183日ルールです。
この183日ルールですが、租税条約に基づく判断についてはよく指摘されるルールです。
一方で、租税条約ではない日本の所得税法において、住所の判定として1年間の滞在日数を問題にするような規定はありません。
確かに、住所以外に、「1年以上引き続いて居所」があれば居住者にする、といった定めはあります。
しかし、現状の税務調査で税務当局が言うような、1年間で183日超日本にいるので居住者、といった規定は見つかりません。
この理由は明記されていませんが、おそらくは源泉徴収の問題があるからと考えられます。
租税条約とは異なり、日本の所得税法では、源泉徴収のルールを細かく定められています。
具体的には、所得を支払った時点で非居住者であれば非居住者として、居住者であれば居住者として源泉徴収をすることになります。
このため、支払った時点でどちらにあたるか判断できなければならないのですが、183日ルールは1年間の実績で判断するものです。
仮にこのルールだけで判断するとした場合、183日を経過することがない6か月までは非居住者として源泉徴収をせざるを得ない、といった問題が生じることになります。
加えて、更に問題になるのは、年の中途で非居住者が居住者になる場合もあることです。
典型例は海外転勤者が年の中途で帰国する場合で、この者は帰国するまでは非居住者、帰国してからは居住者として申告します。
となると、滞在日数だけで判断するとなれば、6か月までは非居住者となってしまう訳で、これまた訳が分からなくなります。
税務調査では、海外と国内を頻繁に行き来する者が居住者になるか非居住者になるかが問題になります。
現状の税務調査は、各年分の滞在日数を調べた上で、183日超日本にいる年は1月1日から居住者となり、同日から居住者として源泉所得税も課税します。
しかし、支払時点では183日超日本にいるかは不明です。
税務調査は過去の年度の税金計算をチェックするものですが、1年経過後の日数を見て、年初に遡って居住者として源泉所得税も追徴するのは違法な遡及課税そのものです。
同様の問題が生じた調査で、担当調査官にこの点指摘しましたら、「滞在日数だけで見ている訳ではありません…」などと苦し紛れの言い訳をしていました。
しかし、滞在日数以外に居住者と認める余地はない調査でしたので、正に遡及課税です。
このため、課税するにしても183日経過後から居住者として課税するなど、早急に税務調査の取扱いを見直すべきでしょう。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。