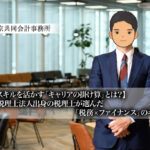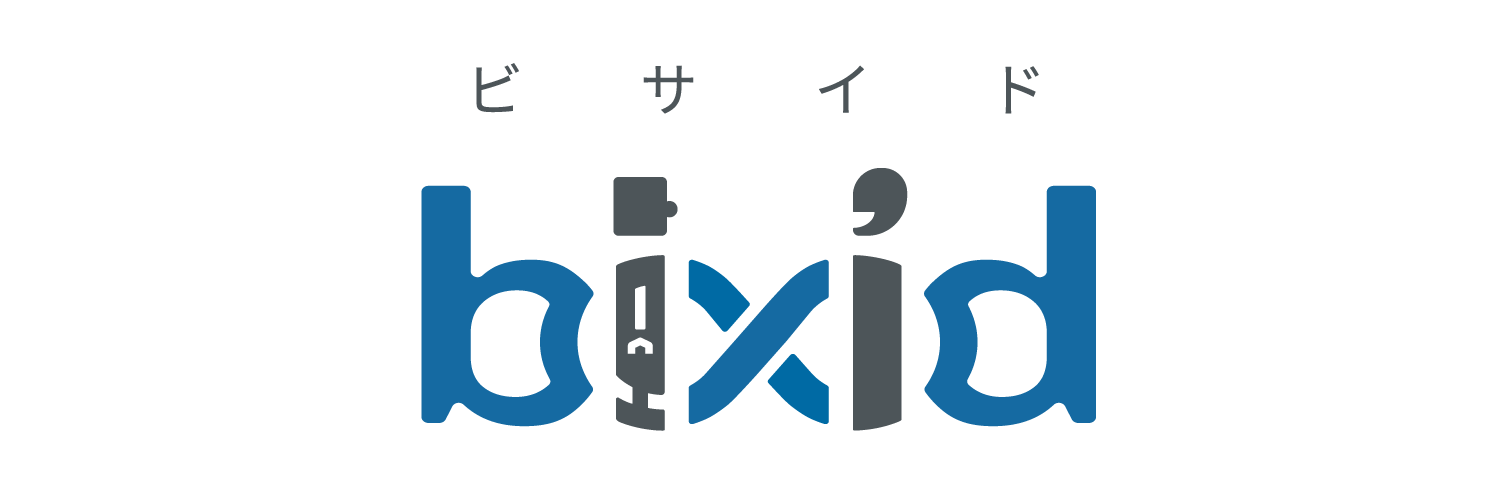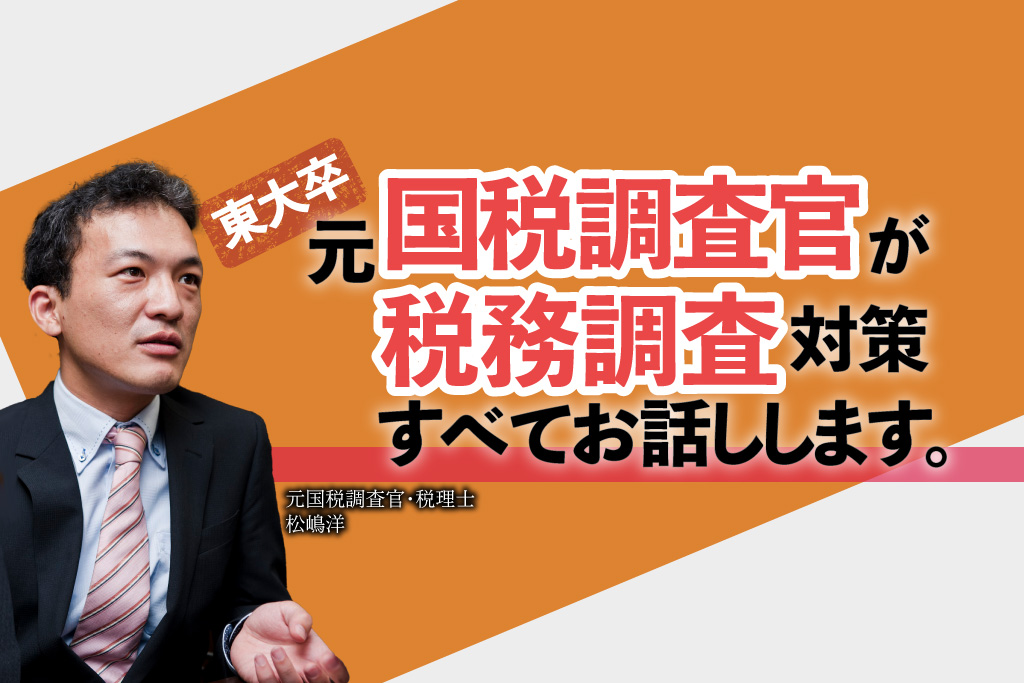
相続税の対象成る、相続財産の評価は、相続税の評価通達で行うことになっています。
その評価通達には、通達による評価方法が「著しく不適当」となる場合には、務当局が別途合理的と考える方法で評価できるという総則6項という規定があります。
しかし、不適当かどうか、税務当局のさじ加減で決められるため、簡単に言えば税務当局の独断でルールを逸脱しても問題ない、というとんでもない内容になっています。
困ったことにそのとんでもない規定による課税を、納税者の権利を守るべき、法の番人である最高裁判所も合法であると認めています。
最高裁判所のお墨付きをもらった税務当局は、従来以上にこの横暴な課税を繰り返しています。
しかし、先日、この規定による課税について、税務当局の処分が違法とされた東京地裁の判決がありました。
この事例においては、相続開始前に租税回避行為と認められるような積極的な行為がないため、この規定を適用できないと判断されています。
過去の最高裁の事例を振り返りますと、銀行に節税目的でマンションを買うと言って融資を受けたり、先が短い高齢者が評価額の安いタワマンを高値で購入したりすることが問題になっています。
これらの行為は、合理的理由がなく税金を下げる行為で問題という判断になっています。
このため、先の地裁判決では、税金を少なくする行為がないのに、単に評価額が小さいという理由だけでこの規定を使って多額の税金をかけるのはやりすぎとして税務当局の処分は違法と判断されました。
結論だけ見ると非常に合理的と思われるでしょうが、実際のところは大きな問題があります。
それは、税金を下げる行為、一般的に「租税回避行為」と言われますが、その行為の意味と範囲がこれまた明確ではないことです。
結局、このような判断がなされても、どこまでが租税回避行為で許されないことになるのか、その線引きは今も全く分かりません。
実際のところ、許されないとされる「租税回避行為」の意義については、裁判所や学者、そして著名な税法の専門家も全く分かっていません。
困ったことに、著名な学者も、日本一の租税法学者である金子宏教授の租税回避の定義について、そのまま租税回避だと言っています。
具体的には、「私法上の選択可能性を利用し~合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら~税負担を減少させ、あるいは排除すること」を意味するとされています。
しかし、学者が書いたものですから、その内容を一般の方が正確に理解することは
そもそも非常に難しいです。
何より「合理的な理由」や「通常用いられない法形式」といった、人によって意見が分かれる曖昧な用語を使っていますので、この意見を「租税回避行為」の基準にすることはできません。
課税の公平の原則から、税法という法律においては統一性が必要になるからです。
このため、6項を適用するなら租税回避行為が必要、などと言われても、何ら問題解決にはなっていないのです。
先の地裁判決を評価する声は大きいですが、実際のところは何にも前向きな解決になっていない、不十分な判決と言わざるを得ません。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。