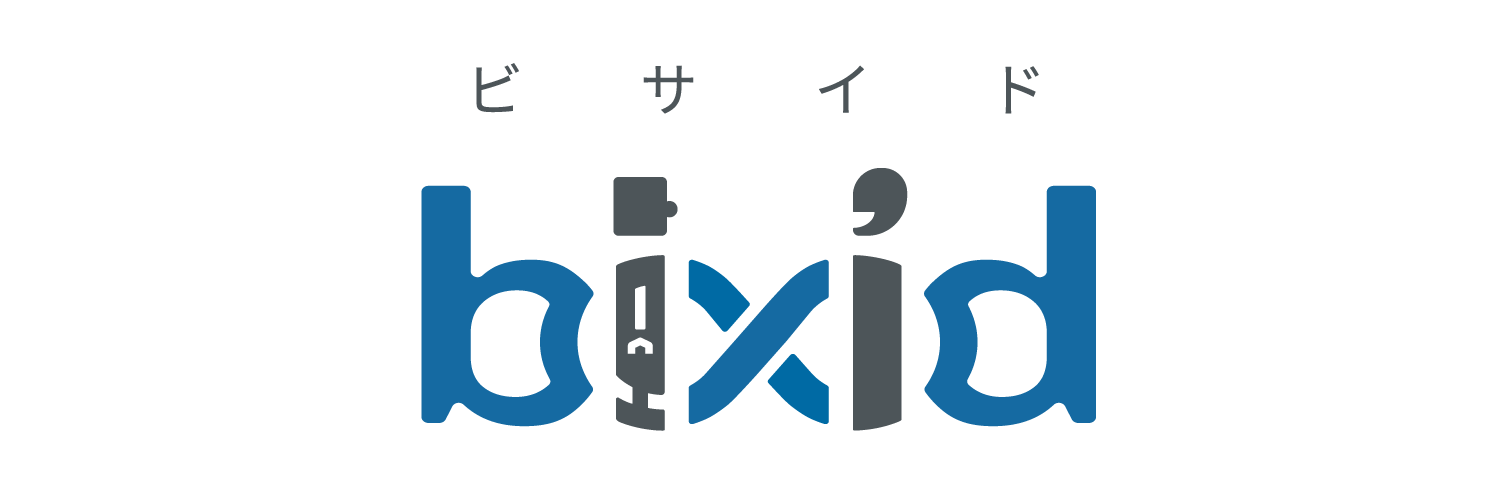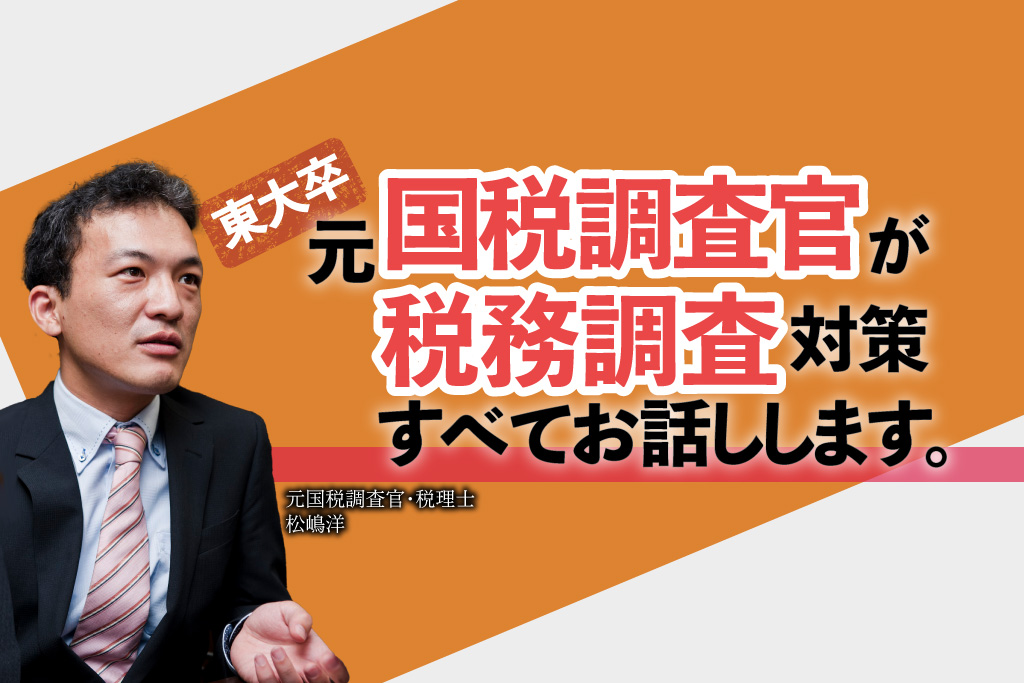
相続財産の評価が「著しく不適当」になる場合には、総則6項という規定によって税務当局が合理的な評価をして相続税を追徴できる、という酷い税務実務が横行しています。
しかし、先日の裁判例において、相続の直前に借金してマンションを買って節税するような、人為的な租税回避行為がなければこの総則6項は適用されるべきでないという判断がなされました。
このため、専門家の中には税務当局がこの規定を適用することに慎重になる、といった好意的な評価をされる方も多いようです。
一見すると妥当な判断のように見えますが、これは税務当局が防止したい租税回避行為を、むしろ助長する判断になりかねないと考えています。
なぜなら、
- 相続の直前に「たまたま」マンションを買わざるを得ない(税金には関係ない)事情があった
- その資金を用意するため「たまたま」多額の借金をせざるを得なかった
- 「たまたま」相続税が下がったので、人為的な要素はなく、租税回避行為ではない
このような言い訳を許すことになるからです。
突き詰めていけば、税金を下げる人為的な行為か否か、この「たまたま」で判断することになります。
「たまたま」が嘘かどうか、それは納税者の内心の問題ですので、税務当局の調査官がその真実を調査するのは極めて困難です。
結果として、税逃れを考える納税者が、「たまたま」でないことの立証義務がある税務当局より、必然的に有利になってしまいます。
ところで、節税のためにマンションを購入するにしても、専門税理士に対するコンサルフィーなど、租税回避行為には相当多額のお金がかかります。
そうなると税金以外にもメリットがあるかどうか、様々なことを検討するはずです。
その検討の中で、極力節税に絡まないものをその取引を行った理由にして、「たまたま」税金が下がりましたと言えば、税務当局が租税回避行為として問題視することが難しくなります。
実際、国税OB税理士や資産税のプロのセミナーなどでは、この点を重点的に解説しています。
具体的には、総則6項のリスクを回避するために、税金には関係ない合理的な理由として、「たまたま」税金が下がったとするよう、(嘘でない範囲での)作り話を作る必要がある、といった解説がなされています。
このような作り話だけで租税回避行為とされるリスクが大きく減り、総則6項の適用がなくなるのであれば、それこそ課税の公平を保つことができなくなると考えます。
冒頭の判例もそうですが、総則6項を租税回避行為の否認規定と誤解するからおかしいのです。
総則6項とは本来、バブルなどで路線価が市場価格を上回ることになった場合、納税者に迷惑をかけないよう「著しく(高額で)不相当」なものを是正する救済措置です。
つまり、納税者にとってありがたい規定ですから、敢えて 総則6項の適用要件は細かく書いていない訳で 、真逆に捉える現状では妥当な結論にはなりません。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。