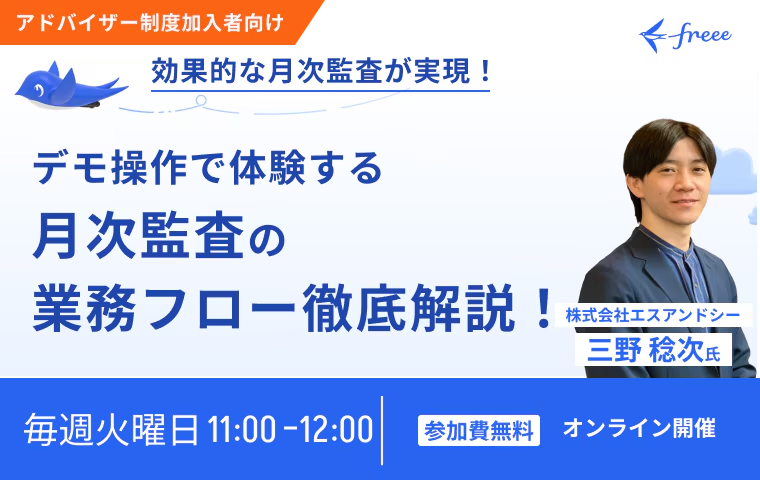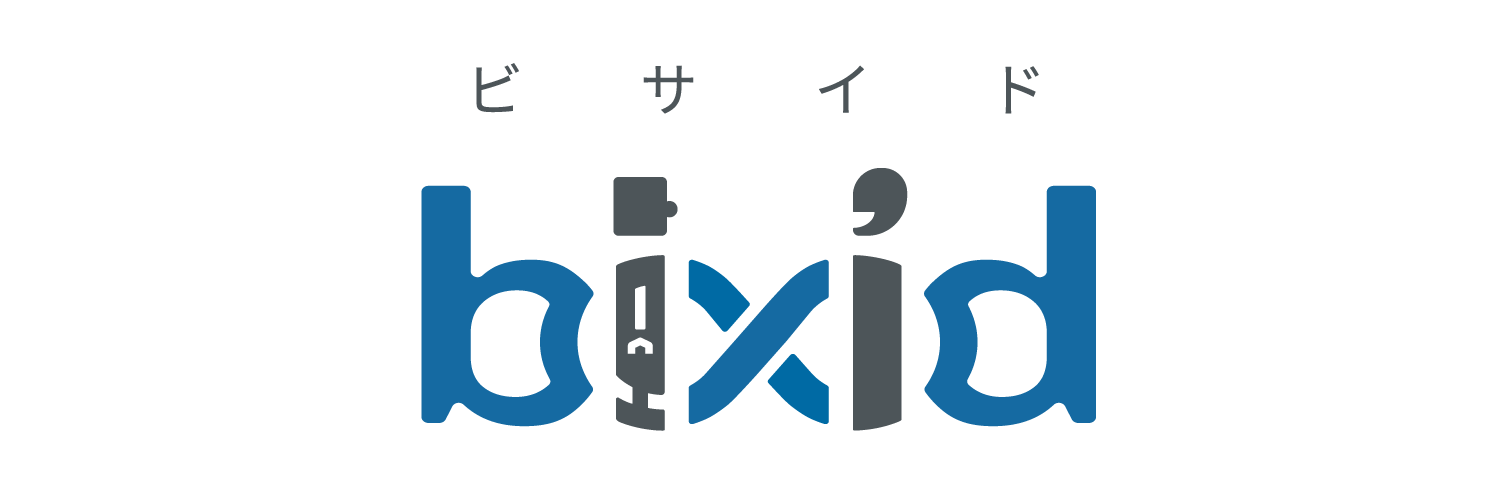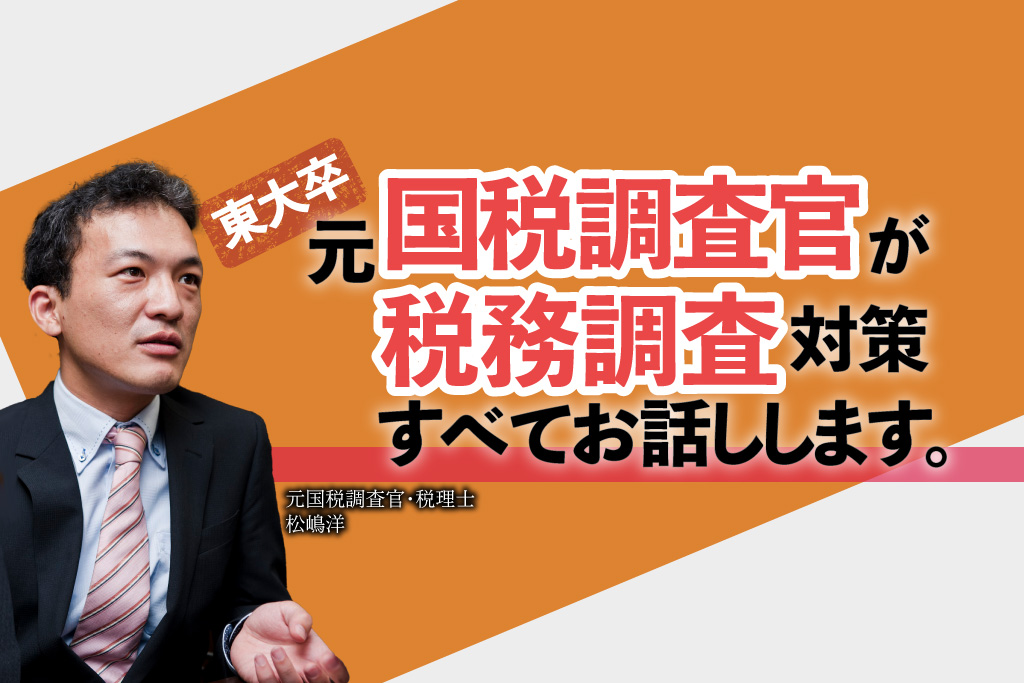
個人の確定申告時必ず問題になることの一つに、為替差益の問題があります。
例えば、個人が1ドル100円で取得した200ドルの現金を持っていて、相場が1ドル120円に上がったタイミングで、その200ドルの現金を使ってアメリカの株式を買うとします。
この場合、1ドルあたり20円円安になっていますので、4000円(20円×200ドル)の為替差益を認識するかどうかが問題になります。
為替差益は雑所得として課税されますので、円安に為替相場が動いている場合、その影響は決して無視できません。
この点、法人の経理ではあまり問題にはなりません。
なぜなら、法人は帳簿をつけていますので、ドルを取得したタイミングも株式を取得したタイミングも、それぞれ円単位の記録をすることになっているからです。
このため、法人なら常に円ベースで考えますので、このケースでも当然に4000円の為替差益を認識します。
しかし、事業を行わない個人は帳簿がありませんし、従来から持っていたドルを株に変えただけで、円が現実に入金された訳ではありませんから、本当に為替差益を認識すべきなのか疑問があります。
とは言え、専門的には税務上の考え方は実は非常にシンプルです。
具体的には、「資産」や「為替」の種類が変われば、為替差益を認識しなければならないというルールになっています。
「資産」というのは、現預金や有価証券、そして固定資産などを意味します。
このため、ドルという現預金でアメリカの建物や米国株式を買った場合、資産の種類が変わるためドル取得時より円安になっていれば、その分為替差益を認識しなければなりません。
次の「為替」ですが、文字通りドルをユーロに換えるようなことを意味します。
我々にとってドルもユーロも外貨であることには変わりありません。
しかし、ドルを取得した時のレートと、それをユーロに変えた時のレートに差があり、為替差益となるのであれば雑所得の申告が必要になります。
交換により、暗号資産の種類を換えると暗号資産の申告が必要とされていますが、その理屈と同じです。
この点、資産や為替の種類が変われば、元々持っていたドル預金などとは、リスクや値動きが変わりますので、結果としてそのタイミングでいったん為替差益を認識すべきと説明されています。
一方、その逆なら為替差益を認識する必要がありません。
例えば満期になったドル定期預金を引き出して、そのドル預金をドルの外貨普通預金として預け入れたとしても、為替差益を認識する必要はないと国税庁のホームページに明記されています。
現金としての「円」で儲かっていなくとも、このように課税される場合がある訳で、外貨ベースの資産運用をする場合には、税務上慎重な判断が必要になります。
す。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。