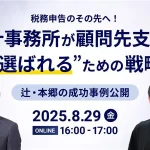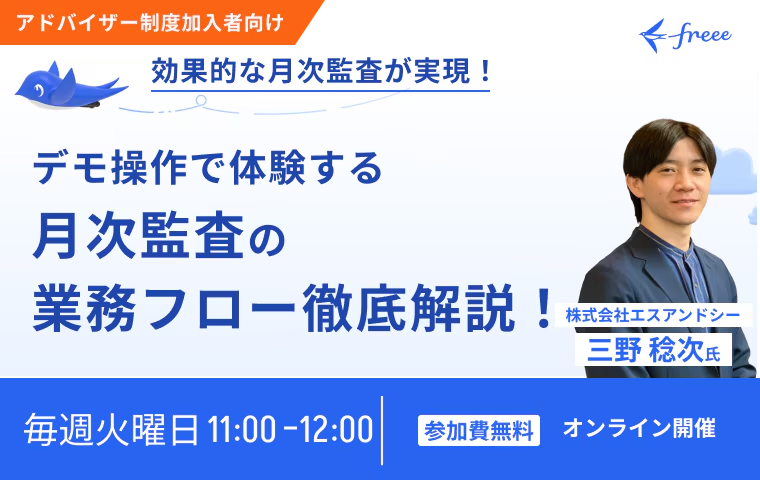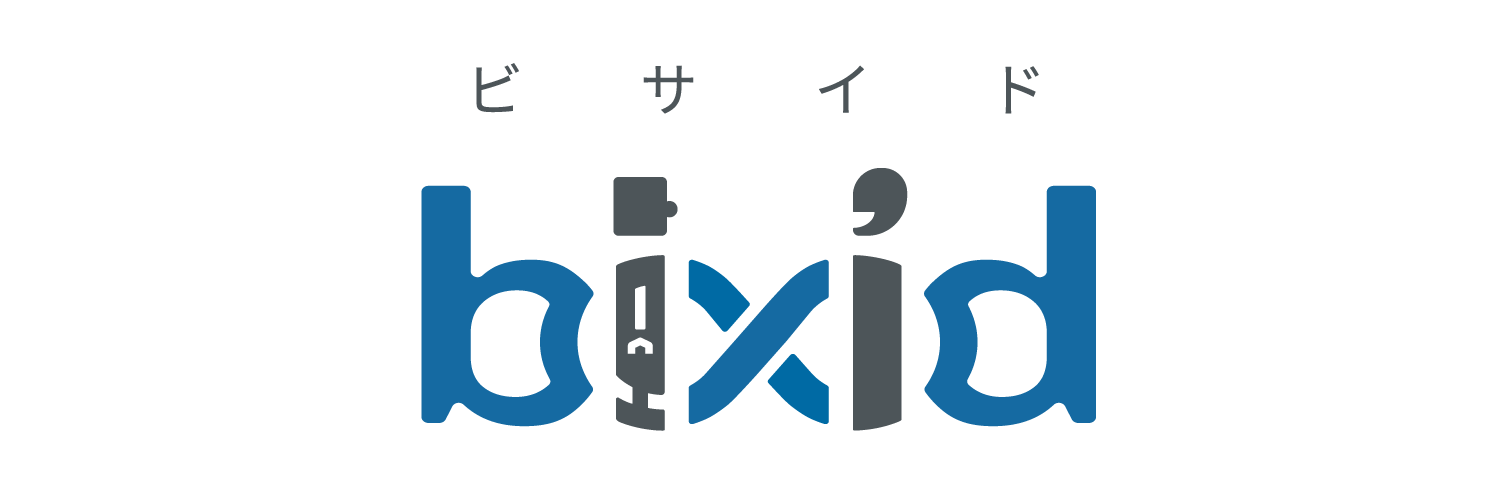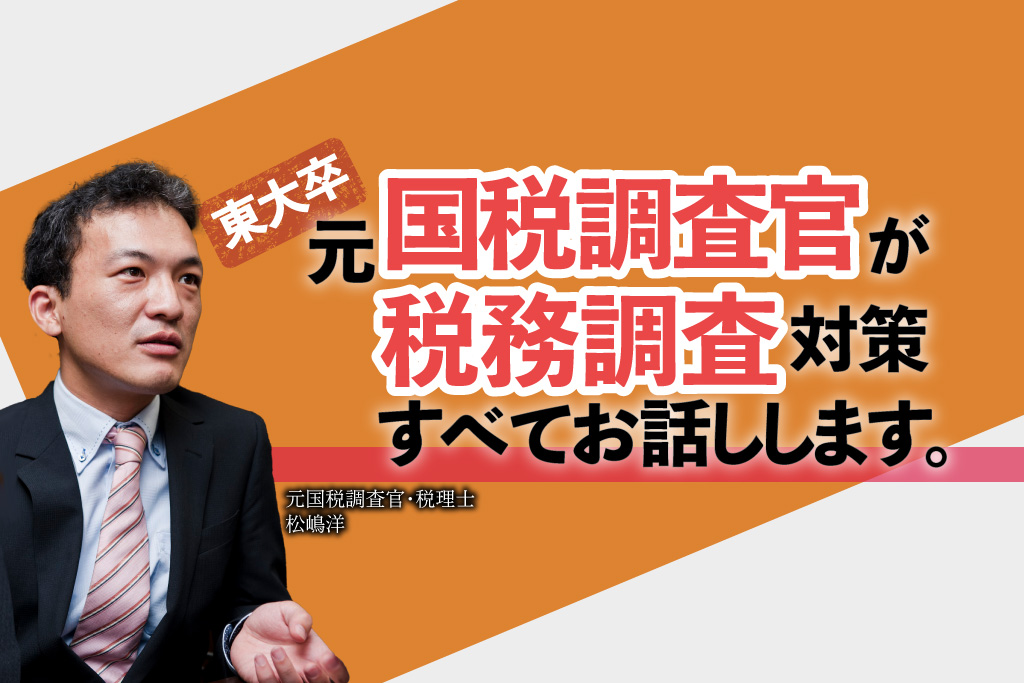
令和6年度改正で、消費税の税抜経理に関する改正が行われています。
消費税が課税される取引について、法人税で処理を行う場合、消費税込みの金額で経理する税込経理と、消費税抜きの金額で経理する税抜経理の二つの方法が認められています。
この税抜経理について、インボイス制度が導入されたことに伴って多少疑義が生じていた部分があり、その点を整理する改正がなされています。
税込110円の商品を買った場合、通常は10円が控除できる消費税ですが、購入先がインボイスの登録をしていない事業者の場合、消費税の控除が認められませんので10円を控除できません。
このため、建前しては、税抜経理でも消費税を負担していないとして商品を110円と記録する必要があります。
しかし、令和11年9月末までは、8円ないし5円を引ける経過措置がありますので、
この経過措置の適用を受ける場合には、商品を102円や105円と記録する必要があります。
となると、取引を区分して、消費税を10円、8円、5円、0円と認識する必要があり、手間が非常に複雑になります。
それに止まらず、支払った10円の消費税に関係なく、売上に対する消費税から一定割合の消費税を控除できる簡易課税や2割特例といった消費税の計算が行われることがあります。
このようなケースは、支払った消費税がいくらなのかそもそもわかりません。
上記のような問題点を踏まえ、令和6年度改正では、納税者の選択に応じ、かなり柔軟に税抜経理を適用できることになりました。
しかし、選択肢が広ければそれだけミスも起こりやすい訳で、改正後の処理も、まだまだ複雑という印象を受けます。
ところで、インボイスを導入する際、多くの税理士や会計士、そして政治家までもが消費税は預り金ではないと主張しています。
彼らが言いたいことは、消費税が預り金でない以上インボイスは不要、ということです。
しかし、預り金でないなら、消費税を区分してはいけませんので、消費税を区分する税抜経理は妥当ではありません。
税抜経理は110円で売上を上げたとしても、10円は消費税を実質的に預かっているので、10円は売上とは言えないという考え方で作られています。
このため、声高に預り金ではない、と言っていた方々は、真っ先に「税抜経理はおかしいので廃止すべき」と主張すべきと思います。
しかし、なぜかそのような声は一向に聞こえてきません。
制度を批判するなら、現状の実務や法令の問題を研究した上で物申すべきですが、こんな勉強をインボイス反対派はしません。
結局、彼らの実態は、気にいらないインボイス制度を何とか取り消すために、安直に消費税は預り金ではない、という理屈を持ち出して騒いでいるにすぎないのです。
追伸、
わたくし松嶋洋の詳しいプロフィールは以下のサイトからどうぞ!!
↓↓↓
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
Twitter:@yo_mazs
⇒「元国税調査官・税理士 松嶋洋が語る!税務署の実態と税務調査対策ノウハウ」の一覧はこちら
税務調査対策ノウハウを無料で公開中!
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋による税務調査対策に効果的なノウハウをまとめたPDFを無料で公開中!ご興味のある方は下記サイトよりダウンロードください。
元国税調査官・税法研究者 松嶋洋とは?
 元国税調査官・税法研究者・税理士
元国税調査官・税法研究者・税理士
松嶋 洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。
現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。とりわけ、平成10年以後の法人税制抜本改革を担当した元主税局課長補佐に師事した法令解釈と、国税経験を活かして予測される実務対応まで踏み込んだ、税制改正解説テキストは数多くの税理士が購入し、非常に高い支持を得ている。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に 税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。